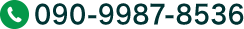-
2022.06-30 / 未分類
予定納税について
個人事業主の方・個人の家主の方、確定申告も終わり所得税の納税も終わり、一息ついていることでしょう。
先日も投稿しましたが、予定納税の通知書が6月半ばに届いている方もいらっしゃるでしょう。
今年の収入が思わしくない場合に予定納税の減額申請を提出することができますが、その提出期限が7月15日です。この日を過ぎると予定納税を支払わなくてはいけません。
再度、ご確認の上対応を検討してみてください。
-
2022.06-20 / 未分類
今月の事務所だよりです
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━
今月の事務所だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━
———————————————————— ———–
◆2022年7月の税務
———————————————————— ———– 7月11日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1
月から6月までの徴収分を7月11日までに納付)7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請8月 1日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市
町村の条例で定
める日)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆住宅ローン控除と譲渡特例
———————————————————— ———– 住宅ローン控除の適用を受けて新住居を取得した人が、旧住居を住
まなくなっ
てから3年目に譲渡して3000万円特別控除の適用を受けようとする場合、住宅ロ
ーン控除が過去に遡って適用されなくなりますので、注意が必要です。 ◆租税特別措置の趣旨は、住宅取得の促進
「公平・中立・簡素」は税制の基本原則ですが、国は、特定の政策目的の実現
のため、特別措置でこの原則を少し緩めて特定の人の税負担の軽減をはかります
。住宅ローン控除は、借入金の金利負担を税額控除で補填するもの、居住用不動
産の譲渡所得の3000万円特別控除は、住宅を売却する人は、代わりに居住用不動
産を取得する必要があることから譲渡所得に係る税負担を減らして、住宅取得を
後押しするものです。他にも買換特例、交換特例などがありますが、これらの譲
渡特例の適用に際し、制度の重複適用は想定されていません。◆会計検査院の指摘で重複適用が発覚
ところで、令和2年度改正前の税制では、居住した年、及びその前後2年間の
重複適用までは禁止されていましたが、旧住居を住まなくなってから3年目に譲
渡した場合、住宅ローン控除と3000万円特別控除の重複適用が起きてしまうこと
を会計検査院が指摘しました。このため、令和2年4月1日以降の旧住居の3年
目の譲渡にも、重複適用はできないこととなりました。◆重複の場合は、3000万円特別控除を優先
重複適用の場合は、3000万円特別控除が優先されます。3000万円特別控除の適
用を受けようとする人が、住宅ローン控除を先行して受けていた場合、過去に遡
って住宅ローン控除が適用できなくなり、修正申告(または期限後申告)が必要
となります。これにより居住用不動産を買換えしようとする人は、住宅ローン控
除と譲渡所得の3000万円特別控除のどちらを選択するか、事前に有利判定が必要
となります。◆控除率1%の見直しも忘れずに
なお、このときの会計検査院報告では、他にも、住宅ローン控除適用者の借入
金利が1%を下回ることが多いことから、ローンで住宅を取得した人の税負担が
金利負担以上に減額される逆ざや現象が報告されていました。そこで令和4年度
税制改正では、令和4年以降に居住の用に供したものから借入残高に対する控除
率は、1%から0.7%に引き下げられることになります。=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆今年も確定申告ですね 歯の治療費と医療費控除
———————————————————— ———– ◆歯科診療で医療費控除の対象となるもの
歯科医師の診療・治療に対する支払で、病状などに応じて一般的に支出される
水準を著しく超えないものは、医療費控除の対象となります。ただ、保険がきか
ないもの(自由診療)や、高価な材料を使用する場合など判断に迷うものもあり
ます。具体的な例を見ていきましょう。(例1)金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費…医
療費控除の対
象(○)
歯の治療のために一般的に使用される材料を使用するのであれば、健康保険の
適用がなく、高額となったとしても控除の対象となります。金やポーセレン(セ
ラミック)は、現在では一般的に使用されているものですので、控除の対象とな
ります。
(例2)インプラント治療・入れ歯(義歯)…医療費控除の対象(○)
(例1)と同じ考え方です。治療等が失われた歯の機能を補う目的の一般的な
ものである限り、控除の対象となります。
(例3)発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正…医療費控除の対象(○)
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必
要と認められる場合、控除の対象となります。
(例4)容ぼうを美化するための歯列矯正の費用…医療費控除の対象外(×)
歯の治療に対する支払ではないので、該当しないこととなります。
(例5)小さいお子さんの通院に付添いが必要な場合の付添人の交通費…医療費
控除の対象(○)
通院費に含まれます。この場合、通院日・金額も記録しておくようにして下さ
い(ガソリン代など、公共交通機関以外を使用した場合の費用は、控除対象にな
りません)。
(例6)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合…その年に信販
会社が立替払をした金額が医療費控除の対象
控除の対象となる医療費は、その年に支払ったものが対象であり、未払のもの
は対象となりません。歯科ローンの場合、治療費を信販会社が立替払をして、そ
の立替分を患者が分割で信販会社に返済します。そのため、信販会社が立替払を
した年のその立替えた金額が控除対象となります。
(例7)歯石・歯垢の除去費用・ホワイトニング…医療費控除の対象外(×) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆領収書と印紙税
———————————————————— ———– ◆領収書と領収証
「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取
った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販
品では「領収証」という記載が多くなっています。ただ印紙税法では、「領収書
」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。本文で
も以下総称として「領収書」といたします。◆領収書と印紙税
領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受
取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するた
めに作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書
」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明
するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入した
ものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明
するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。この17号文
書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。10億円を超え
る金額では20万円の印紙税がかかります。◆売上代金以外の領収書
売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により
印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は5万円未満のものは非課税
で5万円以上のものは200円の印紙税という区分だけです。売上代金以外での金銭
等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領
書等があります。◆営業目的以外の領収書
営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法
人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を
発行しても印紙税はかかりません。=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- -
2022.05-10 / 未分類
予定納税に注意
予定納税とは、年間の所得税が15万円以上の方は所得税を先払いする制度のことです。(個人事業主の件です)
通常売上が多くなって納税額が増えた場合には、所得税を先払いするのは問題ありませんが、今年に限って言うと(特に飲食店など)は、昨年において給付金をもらった事業主様が今回の内容の対象となります。
給付金が多かったので昨年分の確定申告で所得税の納税額が多額になった事業主様で、かつ飲食店であれば、今年の売上がまだまだ元には戻っていない場合に、使える制度があります。
それが「予定納税の減額申請」です。
この申請をすることにより、今年の売上次第では予定納税をしなくてもよくなるか税務署から届いた通知書に記載された予定納税までは支払わなくていいケースもあります。
これについては、現状次第です。また、ある程度今年の売上経費の整理も必要です。これがわからないと申請できません。確定申告終わったばかりなのに、、、と思われる方もいらっしゃるかと思います。
その場合、予定納税を先に支払ったとした場合には、来年の確定申告にて相殺されますので支払うこと自体は問題ありません。
詳細は顧問税理士に相談して対応を検討してください。
-
2022.04-18 / 未分類
今月の事務所だよりです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━
今月の事務所だより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━
———————————————————— ———–
◆2022年5月の税務
———————————————————— ———– 5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付5月16日
●特別農業所得者の承認申請5月31日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税
>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・
地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定
める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆令和3年分確定申告書 すぐ消える変更点
———————————————————— ———– ◆提出が楽になった配当所得の選択制度
上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済の状態で支払
われますが、実際の申告は総合課税・分離課税・(特定口座の場合)申告不要と
課税方式が選択できます。
また、課税所得900万円未満の場合、配当控除の控除率の関係で、所得税と住
民税で申告方式を変えることによってかかる税金を減らせるというテクニックが
存在します。
所得税等の確定申告時には総合課税を選択し、その後市区町村に住民税の申告
書提出等の所定の手続きを行うことで、住民税側は申告不要を選択、という手続
きが取れるようになっていました。さらにこの申請の二度手間を無くすため、令
和3年分確定申告からは、申告書第2表の「住民税に関する事項」に「特定配当等
・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」というチェック欄が新設され、ここに
チェックを付けておけば、市区町村に手続きを取る必要がなく、住民税について
は申告不要を選択できるようになりました。◆ただし、将来選択できなくなります
令和4年度税制改正大綱で「上場株式等の配当所得については個人住民税にお
いて、課税方式を所得税と一致させる」という一文があるため、この改正を適用
する令和5年分の確定申告書は、おそらく今年新設された「申告不要」のチェッ
ク欄は無くなっているものと思われます。◆健康保険料等にも影響がある選択制度
この申告方式の所得税・住民税個別選択については、健康保険料や医療費の窓
口負担割合についても有利な選択ができるため、社会保障制度の公平な負担とい
う面で見ると課題があるため改正されたとする報道もあります。また、金融所得
課税全体の見直しは、令和4年度の税制改正では見送りとなりましたが、その一
環であることも事実でしょう。
今後の税制見直しでも、どの程度、どんな所得や資産を持つ人に、どのくらい
の負担を求めてゆくのかという「公平性」の判断については、議論を重ねて慎重
に決めていただきたいものですね。=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆令和4年度の雇用保険料率2段階引き上げ
———————————————————— ———– ◆2段階で引き上げ改定される雇用保険料
新型コロナの影響が続く中、おととしの2月からこれまでの雇用調整助成金等
の支給額は5兆円を超えていて雇用保険の財源不足が課題となっています。厚労
省の審議会で議論されてきましたが、雇用保険料改定が決まりました。それによ
ると労使折半で賃金の0.2%を負担している失業給付などを支払う事業の保険料
率は4月から半年据え置き、10月から3月まで0.6%上げるとしています。一般の
事業では労使で4月~9月1000分の9.5、10月~3月は1000分の13.5となります。4
月の時点では労働者の給与から控除される保険料は変更ありません。 ◆改定の内訳と流れ
雇用保険料は労使が負担する雇用保険料や国庫負担などで賄われています。雇
用保険料の中身は失業給付(労使折半)、育児休業給付(労使折半)、雇用二事業(
事業主負担、助成金や教育訓練に充てる)で構成されています。 今までは積立金
が一定水準を超えていたことで労働者0.3%、事業主0.6%と原則より低い負担で
抑えられてきましたがコロナ禍で積立金が枯渇してきています。
令和4年度の失業負担分は4月には据え置かれますが10月には0.6になります。
また、育児休業給付に係る保険料率は年間通し0.4%のまま据え置かれます。
一方、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」の料率は4月から0.3%から0.
35%に上がります。その結果事業主負担は全体で0.65%になります。 ◆料率改定事務 変更分はいつから
今のところの予想ですが、令和4年度の労働保険概算確定申告時に令和4年度の
概算額として事業主負担の二事業の引き上げ分を乗せます。また、10月からの料
率改定の分は10月以降の概算賃金額に引き上げられる新料率をかけて保険料の概
算額を出し、前半分と後半分を足して1年間の概算額とします。詳しくは令和4年
度の労働保険料の計算方法が発表されてから確認することとなります。
各労働者の給与からの雇用保険料率の徴収額が上がるのは令和4年10月分給与
からです。=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=- ——————————
—————————— ———–
◆空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例-
———————————————————— ———– 被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がな
く売却する
場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で
空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。◆空き家取壊しのメリット、デメリット
空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に
被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます
。
一方で空き家の取壊しには、工事費用がかかるほか、アスベストの飛散防止を
はかることの行政への届け出、近隣への事前説明など環境に配慮した手続きの義
務が生じます。また、すぐに売却先が見つからずに更地のまま1月1日を迎えた
場合、固定資産税・都市計画税に小規模住宅用地の減免措置(200㎡まで固定資
産税は1/6、都市計画税は1/3に減免)は適用されません。◆特例の適用要件
相続空き家の特例を受けるには、(1)相続開始直前に被相続人が一人で居住し
ていたこと(2)区分所有建物でないこと(3)昭和56年5月31日以前の建築であるこ
と(4)譲渡金額は1億円以下(5)相続開始から3年を経過する日の属する年の12月
31日までに譲渡すること(6)耐震基準に適合するよう空き家をリフォームしてか
ら売却、または取り壊して更地で売却するなど要件があります。◆取壊しは売却前に相続人で行う
以上の要件から空き家の取壊しは売却前に実施しないと特例が適用されません
。売主としては取壊しが面倒なので買主に依頼し、その分、売却価格で調整して
済ませたいと考えたくもなりますが、この場合は譲渡後の取壊しとなるので、30
00万円控除を受けることはできません。
なお、譲渡所得の申告に際し、譲渡日を引渡日とする方法と契約締結日とする
方法を選択できますが、譲渡日を契約締結日とする場合は、空き家の取壊しは契
約前に済ませるよう注意が必要です。◆空き家を相続したときは
3000万円控除を受けるには、特例の適用要件を満たしていることを確認し、解
体業者から工事費の見積りを先に取得します。不動産仲介会社で売却先が見つか
ったときは、売主の側で空き家を取壊すことを条件に解体工事を発注し、売買契
約では更地での譲渡、工事完了後の譲渡日の設定がポイントになりそうです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-
-
2022.03-29 / 未分類
今年の確定申告
多くの方が昨年の確定申告が終わってホッとしているところでしょう。
そして、今年こそはと意気込んでいる方も多くいてることかと思います。
その際に資料の整理も含めて考えていただきたいことがあります。
節税のことも含めて考えていくことが必要かと考えます。その中には、ふるさと納税・倒産防止共済の加入・小規模共済の加入などなどあります。
また、車の購入も早い目に考えていかないといけないと思います。
申告が終わった時期だからこそ、自社の事業を見つめなおす時期としてみてはいかがでしょうか。